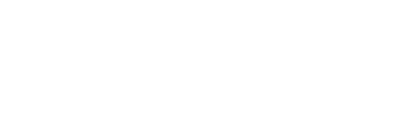智恩寺とは
智恩寺は、『日本三景天橋立』に対面する景勝の地に立つ禅寺。天橋立は海を走る全長3キロメートル余りの砂州に松が生い茂り、その姿は天につながる橋や龍にも譬えられる奇観である。古来より日本有数の観光名所として知られ、現在も日本三景のひとつに数えられている。智恩寺はその立地に加え、永い歴史を物語る建造物や美術品が数多く遺されており、今も大勢の参拝客が訪れる。
創建の由来については神代にまで遡るとされ不詳だが、延喜四年(904年)に醍醐天皇より『天橋山智恩寺』の号を賜った。本尊の文殊菩薩は『日本三文殊』としても広く知られ、その智恵を授かろうと志望校合格や学問成就などを祈願する参拝客も多い。
毎年7月24日の出船祭は文殊菩薩の例大祭であり、夜間のライトアップにより美しく照らされた境内に僧侶の読経の声が響き渡る。春には釈迦の誕生を祝う『花まつり』が行われ、文殊堂が美しい花々で彩られる。境内には自由に歩く愛らしい猫たちがいて、智恩寺を参拝する楽しみの一つとなっている。
重要文化財木造文殊菩薩
脇侍善財童子優闐王像
智恩寺の本尊は智恵を象徴する文殊菩薩であり、文殊菩薩がインドから中国へと旅をする姿を表している。獅子に乗る文殊菩薩を中心に左右に善財童子と優闐王を脇侍とする三尊形式。善財童子は智恵の象徴である経箱を捧げ持ち、優闐王は獅子を牽いる姿として表される。
制作されたのは鎌倉時代(1185~1333年)。細かい盛り上げ彩色の文様を施していることや、文殊菩薩の高く結い上げた宝髻、張りと柔軟さを感じさせる肉身の表現などに鎌倉時代後期の特色が現れている。
重要文化財鉄湯船
現在は手水鉢として使用されるが、もとは寺院の湯舟として制作されたもの。
鎌倉時代の正応三年(1290年)に興法寺(弥栄町)のために作られたが、その後智恩寺に移された。
鋳出銘より山河貞清が鋳物師として制作に携わったことが判り、巨大な湯船にもかかわらず、薄い鉄層を使っているところに、山河の熟練した技が現れている。
重要文化財多宝塔
方形の初層の上に円筒形の上層を重ねた2階建ての塔に、宝形造の屋根と相輪を付けた塔婆を多宝塔という。智恩寺の多宝塔は、室町時代(1336~1573年)に建立されたものとしては丹後地方唯一の遺構。中央に祀られる大日如来(京都府指定文化財)は真言密教における根本仏で、大宇宙の象徴とされる。塔の屋根は、薄い木の板を何層も重ね合わせる古来の技法を用いた杮葺であり悠然と反り返る軒が、優雅な外観を生み出している。
重要文化財金鼓
銘文から、1322年に韓国の寺の什物として鋳造されたものであり、丹後地方と朝鮮半島との間の交易をしめす資料となっている。日本の鰐口に似た形状だが、吊環が3カ所にあることや、周辺部を蓮弁文や唐草文様で覆っているところなどに本邦との違いが見られる。