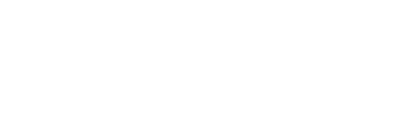觀音寺とは
奈良時代(720)にインドの帰化僧法道仙人によって開創。本尊十一面千手千眼觀世音菩薩を祀る。平安時代(961)空也上人によって七堂伽藍を整備。よって中興の祖とする。最盛期は鎌倉時代25余坊の寺院をもつ中本寺となり栄えた。
現在は日本最古級の木造不動明王立像を祀る寺として、また歴史ある花と文化財の寺として多くの方から親しまれている。別名「丹波あじさい寺」と呼ばれ、特に6月〜7月にかけては100種一万株のあじさいで花浄土と化す。
重要文化財木造不動明王立像
不動明王は弘法大師空海によって唐から請来された仏像である。觀音寺の不動明王立像はその平安時代初期9世紀にまでさかのぼる。
立像としては国内で現存する最古級の不動明王立像であり、日本の仏教美術史の研究にも欠かせない。2023年、重要文化財に指定。カヤの一木造で、檀像風。炎髪と迫力ある面貌、腰をくの字に曲げた生動感あふれる姿に特徴がある。両脇の二童子立像も、平安・鎌倉時代の古仏で貴重である。