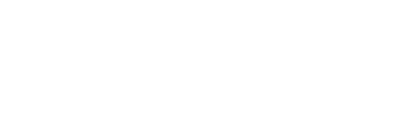多禰寺とは
1400年余りの歴史を持つ由緒ある建造物、多禰寺。飛鳥時代(592~710年)以前の587年に現在の京都府舞鶴市に創建され、皇室や有力大名の庇護を受けた。今は、郊外の風光明媚な山間にひっそりと佇む。多禰寺は西国四十九薬師霊場のひとつでもある。各霊場には病気を平癒する薬師如来が祀られ、特に目や耳の病気の治癒を祈願する参拝者が多い。
丹後地方には、用明天皇(?~587年)の三男である麻呂子皇王(当麻皇子)が、国を脅かしていた鬼を退治し、七仏薬師をそれぞれ安置する寺を造立したとする伝説があり、多禰寺はそれらの寺のひとつでもある。
現在の優美な旧本堂は、1824年に再建されたもの。境内には数多くの文化財がある。特筆すべきは、仏を守り導く役目を担う2躯の木造金剛力士立像。国内有数の大きさを誇り、国の重要文化財に指定されている。
重要文化財木造金剛力士立像 2躯
金剛力士を体現した、寄木造の立像。金剛力士は仁王(2体の守護神)とも呼ばれ、ほかにも門の左右に仁王像がそびえ立つ寺院は多い。多禰寺の仁王像は高さ3.58メートルと3.56メートルで、国内有数の大きさ。鎌倉時代(1185~1333年)に制作され、当初は多禰寺の門のひとつに立っていたが、後年、安置用に建てられた宝物殿へと移った。ともに上半身裸体で生々しい迫力を放ち、写実的に表現されている。憤怒に燃える目とその立ち姿からは、力強さが感じられる。