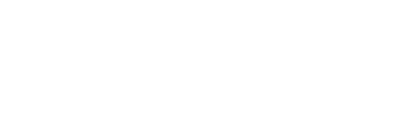縁城寺とは
寺宝『縁城寺縁起』に、「養老元(717CE)年 当寺開山善無畏三蔵 入朝の時(中略)紫雲たなびく当山の四方の谷を 十八善神が守護し 観音の輝き赫赫として満月の如し 三蔵喜んで由来を問い給い ご尊像を授かり給う」とある。
光仁天皇は宝亀二(771CE)年堂宇を建立し「千手院」と名づけ賜う。また、一条天皇は永延二(988CE)年、勅願寺となし賜う。更に、桓武天皇は延暦14(795CE)年「縁城寺」の寺号勅額を賜う。
弘法大師は、若き日当寺に来錫され、「發信貴山」との山号額を自ら書き残し賜う。
爾来、丹後の古刹として、勅使門より金堂までの三百メートル余に、七ヶ院二十五房谷に満ち香煙絶えることなく、「橋木の観音さん」として丹後地方の信仰の中心として栄えた。三度の大火にも関わらずその都度再興された。
木彫千手観音立像、石造宝篋印塔は国の重要文化財、その他京都府指定文化財、登録文化財、京丹後市指定文化財等多数を所蔵し、一部は十月十八日に宝物虫干し展示を行っている。
また、縁城寺は明治維新までの千年余の間、集落の式内神社「橃枳(からたち)の宮」の別当として司祭してきた。
「發信貴山(はしきさん)」「縁城寺(はしきでら)」「橃枳宮(はちきのみや)」は、集落の地名「橋木」に深く関与し、この集落由緒を語るキイワードである。
重要文化財木彫千手観音立像
縁城寺ご本尊、秘仏としてご開帳は、不定期で特別行事のみ。顔の表情は平安時代前期の特徴を表しているが、衣紋の彫刻の浅い点や胴体のくびれ等にやや後の特徴が顕れている。素木一木造で内矧ぎ無し、三弁宝冠を着け頭上面が無い(所依の経典による)、木の節をそのまま残して彫刻している、全身にノミ目を留めている、歪みの造形等、合掌手と捧鉢手は胴体と同部材であるが、他の脇手、台座は別材でほとんどが後補である。像高152cm。
重要文化財石造宝篋印塔
宝篋印塔は、如来の心秘密を説いた『一切如来心秘密全身陀羅尼』を内部に納めた七宝塔で、この塔を礼拝供養する者は、地獄の門を閉じ、重罪一時に消滅して菩提を得る。また現世の諸難を免れ、無量の福を得るという功徳が説かれている。「正平六年 仏子行秀」と刻銘があり、善無畏三蔵の供養のために建立されたものである。
台石の格狭閒及び蓮弁等に時代の特徴が表れており、正積みの基壇を持つ宝篋印塔に完存した堂々たる遺構である。総高313.9cm、基礎一辺227.6cm。